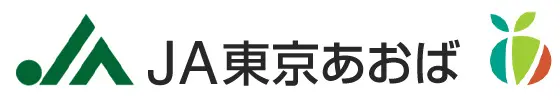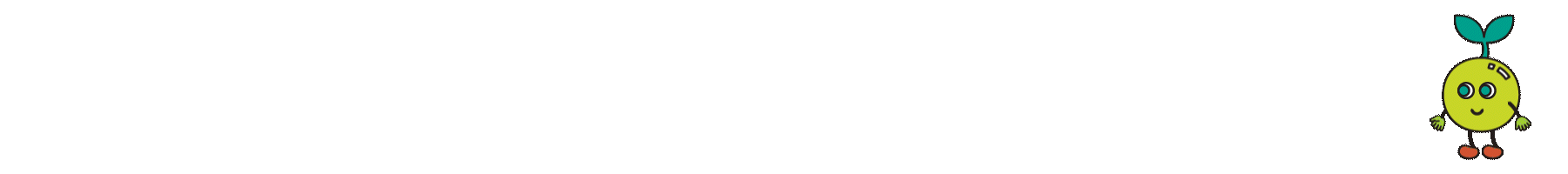活動報告ブログ

手作りのおまんじゅうを子どもたちに
板橋地区女性部は4月9日(水)、赤塚支店調理室で田舎まんじゅうを作り、区内のこども食堂へ寄付しました。この田舎まんじゅうは板橋農業まつりや農業祭で毎年行列ができる人気商品で、今回は同部員12名で手作りした100個のまんじゅうを届けました。
子ども食堂の秋元すがよ代表は「美味しいと評判で毎年楽しみにしており、ぜひまた来年もお願いしたい」と話しました。
女性部本橋玲子部長は「あたたかい手作りのおまんじゅうで子どもたちが喜んでくれたら嬉しい。地域の子どもたちにできることを今後も探していきたい」と話しました。

野菜の収入増 探求 練馬区田柄 相原謙介さん・尚悟さん
練馬区田柄の相原謙介さんと弟の尚悟さんが営むあいはら農園では、トマトのハウス栽培(養液栽培)を始めて今年で3期目となります。露地栽培に比べ、ハウスを利用することで効果的な害虫防除と環境制御、以前より長くトマトを栽培できることなどから、収入は2倍程度まで増えた。
相原家は450年以上続く歴史のある農家。代々、露地栽培が主であったが、謙介さんは「こんなに頑張っているのに収入につながらない」と感じ、限られた面積で単収を上げるために、畑の半分をハウス栽培に変えた。
トマトハウス栽培は、尚悟さんが主に担当しています。 尚悟さんはオンラインセミナーに参加し、環境制御や生体反応について積極的に学んでいます。昨年、江東区の東京ビックサイトで開催された施設園芸・植物工場展「スマートアグリジャパン2024」にも参加し、新しい肥料や資材の知識を増やしています。
昨年のハウス栽培の出来は、水の量や肥料の量を変えたため、味は良くなったが収量が落ちたそうだ。この原因を環境制御と、猛暑によるハウス内の温度上昇が関係したと尚悟さんはみています。「次回作付け時は、新しくバイオスティミュラントと呼ばれる根に効果を発揮する資材を定植時に導入したい。植物が本来発揮する能力を引き出したい」と意欲を見せています。
一方で、謙介さんは露地野菜に注力しています。昨年は暑さでネギがうまく育たなかったが、「なべちゃんねぎ」は立派に育った。暑さにも強く、冬の寒さでも葉のダメージが少ない品種を選定したためです。
謙介さん尚悟さん兄弟は、環境制御や品種選定など、日々試行錯誤を繰り返しています。「より良いトマトになっていく過程を感じてほしい」と消費者へ向けて話す尚吾さん。まだまだトマトハウス栽培への挑戦は続きます。

直売所出荷者を紹介する冊子「ツクリテ」完成!
当JAは、4カ所展開する農産物直売所の出荷者95人を紹介する冊子「ツクリテ~生産者の手と消費者の手をつなぐ~」を作成し、3月末に完成しました。4月から支店、直売所、子会社の東京協同サービス(株)で配布します。誌面には、出荷者の顔写真、出荷先、主な作物を掲載している他、掲載者の人柄が伝わるように、趣味なども盛り込んでいます。
冊子は、若手職員を対象としたプロジェクト「第3期NEXT AOBA PJ」の活動の一環。「協同活動の実践」をテーマに、組合員・地域住民・職員の3者がメリットを感じる活動をめざし、メンバーである若手職員10人が企画しました。組合員からの「自分の住んでいる地区以外の若手就農者や普段馴染みのない生産者の顔と名前が一致しない」という声を反映し、作成に至りました。
直売所委託販売契約者200人を対象に掲載意向調査からはじめ、製作期間は、約半年にわたりました。メンバー以外の職員も協力し、取材・撮影を行いました。取材時は、初めて会う生産者もいて、不安を感じるメンバーもいましたが、温かく迎えてくれました。また、生産者から良い撮影場所のアドバイスをもらうなど、和やかな雰囲気で取材・撮影を進めていきました。
主管部署である経営企画課部齋藤祐一部長は「生産者には、生産者同士のつながりをこれまで以上に深め、地域住民には、生産者の顔が見えることによる、安全・安心な農産物購入の機会を提供し、JA職員には、組織を支える生産者をしっかりと認識し、組合員や職員とのコミュニケーションのきっかけとすることを期待したい」と話しました。
プロジェクトリーダーを務める石垣翔太郎係長は「JA東京あおば管内は、今も多くの農地が残っている。地域住民の方に、直売所に出荷されている生産者を知ってもらいたい。この冊子を見て、生産者の人柄や想いを知ることで「推し農家」を見つけ、都市農業を応援してほしい」と話しました。
ツクリテは各支店窓口にございますので、ぜひご覧ください。


栽培体験コース(第1回) ジャガイモ植え付け
3月下旬、練馬区立高松みらいのはたけで、ジャガイモの植え付け体験イベントを行いました。参加者はジャガイモ栽培体験コースに申し込みをした60組。種まきから収穫までの農のサイクルを知ってもらうため、全3回のコースを体験する予定です。今回はコース1回目として、ジャガイモ(品種:キタアカリ)の植え付けを体験しました。
参加者はあらかじめ敷かれたマルチに穴を開け、1組あたり8個の種イモを植え付けしました。体験の前に、同職員が、種イモの目やウイルスフリーのジャガイモについて説明。今回はSサイズを使用し、MやLサイズの種イモは2つに切って植え付けをするなどを伝え、ジャガイモの植え付けを肌で感じてもらいました。
参加者は「小さなSサイズの種イモから、たくさんジャガイモができるのは驚いた。今から収穫するのが楽しみ」と話しました。
同園は、練馬区が「農の景観を区民とともに育て・守る」をコンセプトとして開園した区立の畑。当JAが練馬区から委託を受け管理運営しております。土曜、日曜日問わず開園時間内(午前9時~午後5時)は、自由に園内で作物の成長を見学できますので、お気軽にお越しください。

板橋地区女性部 備蓄食品の販売イベント開催
板橋地区女性部は3月10日~18日、板橋地区アグリセンターとファーマーズショップにりん草で備蓄食品の販売イベント「おうちで備えるキャンペーン」を開きました。地域住民に向けた防災活動を企画する中で、同部役員の発案で板橋区地域防災支援課に相談し、区の事業として行っている同キャンペーンに参加しました。JA店舗で備蓄食品を揃えて販売しました。
当日は女性部員が店頭に立ち、備蓄食品の試食、抽選会の実施や※ローリングストックの呼びかけなどを行いました。(※普段の食品を多めに買い置きし、古いものから消費して消費した分買い足すことで、常に一定量食品が備蓄されている状態を保つ方法)
同部本橋玲子部長は「全国で規模の大きい地震が増えています。多くの方にローリングストックの考え方が浸透するよう、今後も呼びかけたい」と話しました。同部では今後も継続的に地域住民が防災について学べる機会を企画していく予定です。

消費者と生産者のために 野菜詰め放題開催
練馬地区アグリセンターとふれあいの里では、3月10日(月)から14日(金)の4日間、「決算お客様大感謝祭」と題し共同イベントを開きました。両店舗でそれぞれ2,000円以上の会計をしたお客様に米の一部銘柄を1割引きで販売するほか、練馬区内産農産物の詰め放題を500円で実施。ふれあいの里の詰め放題は17日まで開きました。
詰め放題は、農産物価格の高騰が続くなか、手に取りやすい価格帯で販売し、地場産農産物をPRするほか、3月は生産者が次の作付けに向けて畑に残っている冬野菜を片付ける時期であり、それらをJAが買い取り販売することで、生産者の所得向上を目的としています。
初日の10日、詰め放題ブースにはニンジンやミニトマト、リーキなど様々な野菜が並べられ、練馬地区アグリセンターでは59人が詰め放題に参加し盛況となりました。
企画した岩井則幸センター長は「農産物価格の高止まりが続いているが、こうしたイベントを通して地場産の魅力を再発見してほしい。今後もお客様がワクワクする店舗をめざしていきたい」と話しました。

熟成させることでさつまいもの糖度がアップ!(ショート動画)高橋範行さん
今回のショート動画は、石神井地区で有名な「ベジファームかのん」の高橋範行さん。
今回は、「熟成さつまいも」にクローズアップ!熟成させることでさつまいもの糖度が増え、甘味が増します。
ぜひ、ご賞味ください。(画像をクリックするとショート動画が流れます)

教育文化活動の重要性を再確認
JA東京あおばは3月1日(土)、石神井支店で令和6年度教育文化活動セミナーを開きました。地域に根ざすJAとして教育文化活動の重要性を再確認することを目的に、JA役職員や青壮年部員、女性部員らが参加しました。
一般社団法人家の光協会より2人が講師を務めました。「『家の光』の活用」と題して、共通の物差しを基にした会話の重要性について話し、事業部ごとに活用できる記事を紹介しました。
また、組合員の発表として、女性組織活動体験発表を大泉地区女性部の加藤優子さん、青壮年組織活動実績発表を大泉地区青壮年部の髙橋徹さんが発表しました。
参加した職員は「家の光を活用し、部署内や組合員とのコミュニケーションづくりを大切にしていきたい。組織部会の活動内容を知る良い機会となりました」と話しました。


営農の省力化・効率化へ管理機等の実演会
JA東京あおばは、組合員からの要望を取り入れながら定期的に農機実演会を開いています。2月26日(水)には、今年度2回目となる実演会を開きました。今回は、管理機のアタッチメントについての内容で、クボタアグリサービス(株)のほか、(株)藤木農機製作所、(株)宮丸アタッチメント研究所の担当者を講師に招き、組合員7人が参加しました。管理機の基本的な仕組みやマルチャーについての説明を中心に、畝立て機や培土機等、アタッチメントそれぞれの用途や特徴について説明がありました。参加者らは、実際に畑で動く様子を見て、手で触れて、体験していた。参加した若手生産者は「実演を見ることができ、自分が使うイメージが湧きました。管内でこうした機会があるのもありがたい」と興味深く多くの質問を投げかけていました。

青壮年部若手がマルシェ開催
練馬地区青壮年部若手メンバーでつくる「NERIMA Farmer‘s Merket」は2月20日(木)、練馬区役所アトリウムでマルシェを開きました。区内産のダイコンやキャベツ、ホウレンソウなど葉物野菜や珍しい野菜、地元飲食店の弁当などが並び、10時の開店前から多くの来場者が訪れました。
同青壮年部の若手が、地元の消費者や練馬の農産物を伝えられる場所をつくりたいと「NERIMA Farmer‘s Merket」を2017年に結成しました。
マルシェの参加者は「区役所の用事ついでに訪れてみました。普段なかなか手に入らない珍しい野菜もありとても楽しい。今後も区役所でのマルシェに期待したい」と笑顔で話しました。